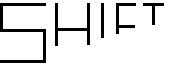小山泰介
PEOPLEText: Mariko Takei
常に変化を遂げている無機的な巨大な生命体とも言える“都市”から有機的な現象を捉えて写真作品を手掛ける小山泰介。2003年から写真家として活動を開始し、2006年から手掛ける「entropix」など、都市を有機体と捉える写真シリーズを発表。現在、世界中で注目を集めている、若手写真家の一人である。8月のシフトカバー作品と共に、これまで手掛けた作品や今後の活動について紹介する。

まず自己紹介をお願いします。
小山泰介。1978年生まれ、東京在住の写真家です。
物事が変化する過程や、都市の中の自然現象などに興味を持って製作しています。
写真作品を手掛けるようになった経緯を教えて下さい。
学校では自然環境について勉強していましたが、2003年10月から本格的に写真作品を製作するようになりました。大きなきっかけはデジタルカメラを手にしたことです。デジタル化によって自宅でプリントやポートフォリオ、本などの製作をすることが可能になりました。
都市を有機体と捉える写真シリーズ「entropix」や「Rainbow Form」、「Starry」そして新作の「Melting Rainbows」がありますが、それぞれからいくつか作品をご紹介頂けますか?

Untitled (O) / 2007 / From the series of “entropix”
「entropix」(2006年~)は、 建設や解体、区画整理、再開発といったことを繰り返しながら変化し続けてきた”東京”という街を、都市と自然が渾然一体となって新陳代謝する有機体のようなものとして捉え、 東京の街を歩きながら様々な人工物の表面やそこで起こっている現象にクローズアップしたシリーズです。「entropix」というタイトルは、“entropy”と“picture”、“pixel”を合わせた造語で、都市のエントロピーを写真化したものという意味が込められています。
撮影していた時期がちょうど東京ミッドタウンや国立新美術館、ららぽーと豊洲、ラゾーナ川崎など大型商業施設が続々とオープンしていた時期で、東京ミッドタウンの工事現場周辺を歩くことも多かったです。

Untitled (Rainbow Form 2) / 2009 / From the series of “Rainbow Form”
「Rainbow Form」(2009年)は虹のグラフィックが使われた広告ポスターにクローズアップしたシリーズです。虹という光の現象が商業広告のイメージとして街中に貼られているということや、晴れた日に太陽光を浴びた印刷物の虹が、まるで都市に発生した自然現象としての虹のように見えたことなどが、集中して撮影をするきっかけでした。
続きを読む ...