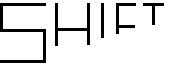横尾忠則 連画の河
HAPPENINGText: Alma Reyes
現在、国際的に高く評価されている著名な日本人現代美術家の中で、おそらく最も神秘的で非凡な存在である横尾忠則。彼の絵画は、意図することなく、また予期することなく、その筆致によって自然に導かれ続けている。彼の原動力は、その時々の身体、心、体調から感じられるものだ。29歳(1965年)で第11回毎日産業デザイン賞を受賞したのを皮切りに、第6回パリ青年ビエンナーレ・版画大賞(1969年)、第4回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・ユネスコ賞(1972年)、 ニューヨークADC賞・金賞(1997年)、紫綬褒章(2001年)、第27回高松宮殿下記念世界文化賞(2015年)、2020年東京都名誉都民……等々、88歳の横尾は紛れもなく空前絶後の人間国宝である。世界各地での個展やグループ展の数も唖然とするほど多い。
さらに横尾は、正式な美術学校での教育を受けず、独学、実験、そして多種多様なメディア、テーマ、イメージ、影響を絶え間なく探求することによって、独自の方向性を確立した完全な独学者であり、同世代で最も精力的に活動するクリエイターの一人である。

横尾忠則のポートレート Photo: Kazunari Tajima
6月22日まで、世田谷美術館で「横尾忠則 連画の河」が開催されている。友人たちとの再会の写真から始まり、生と死が氾濫する川の流れのように、浮かんでは沈む多彩なイメージへと展開する64点の新作による展覧会である。
連歌とは、和歌の上句と下句を数人で分担して詠み合うものであるが、2023年春、横尾は自身の体の衰えに淡々と応じつつ、大きなキャンバスに向かううち、「連歌」ならぬ「連画」制作が始まった。横尾は昨日の自作を他人の絵のように眺め、そこから今日の筆が導かれるままに描き、明日の自分=新たな他者に託して、思いもよらぬ世界がひらけるのを楽しんでいた。横尾にとって「連画」は、川の流れのように、ある段階から次の段階へと横断していく。
『ぼくの場合は絵ですから、まず1点描きます。その1点から連想されるイメージを待ち、次の2点目を描く。そのようにして、3点目、4点目と続けて、とうとう64点になりました。複数の人たちのあいだで、わかりやすくいえば「しりとり」式に歌を増やすように、ひとりの画家が、自分の絵で「しりとり」をして連ねていく。だから「連画」なのです。』 – 連画の河は輪廻の海に注ぐ 横尾忠則へのインタビュー 聞き手・構成 塚田美紀(世田谷美術館学芸員)

横尾忠則《記憶の鎮魂歌》1994年 横尾忠則現代美術館蔵
作品は、横尾の創作意欲の中にある「川」の流れをとらえるため、制作日順に並べられている。このシリーズは、篠山紀信が1970年に撮影した写真をそのまま使用した《記憶の鎮魂歌》(1994年)から始まる。横尾の故郷である西脇(兵庫県)の川沿いの橋の下で、同級生と一緒に写っているこの写真は、その後22年後に出版された作家の伝記的写真集『横尾忠則 記憶の遠近術』に、1970年に自決した三島由紀夫が遺していた横尾論(序文)と共に掲載された。
『会場で、あるいは今回のカタログでじっくり観ていただければわかるかと思いますが、点数が増えるにしたがって、鉄橋の下に並んでいた同級生はバラバラに散っていき、はたまた新しいキャラクターに変貌したりして、自由に、勝手気ままに動き始めます。気づいたらデュシャンやマン・レイになったり、なぜだかメキシコの人になったり、ゴーガンのタヒチの女たちになったり。描いているぼく自身が、このことに驚いています。あまりに勝手に行動し、変身してしまっていますが、画家であるぼくにも彼らを束縛することはできないのです。そして今思うのは、64点全作で1点なんですね。それも一種の時間芸術といいましょうか。』 – 連画の河は輪廻の海に注ぐ 横尾忠則へのインタビュー 聞き手・構成 塚田美紀(世田谷美術館学芸員)
続きを読む ...