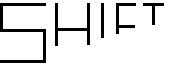モダン・タイムス・イン・パリ 1925 ― 機械時代のアートとデザイン
HAPPENINGText: Alma Reyes

「モダン・タイムス・イン・パリ 1925 ― 機械時代のアートとデザイン」展示風景より、ゲブリューダ・トーネット《ウィーンチェア(No.209)》1970年 [1870年]、武蔵野美術大学 美術館・図書館 / ル・コルビュジエ、ピエール・ジャンヌレ、シャルロット・ペリアン《シェーズロング(No.LC4)》カッシーナ[トーネット社] 1975年 [1928年]、武蔵野美術大学 美術館・図書館 / ル・コルビュジエ、ピエール・ジャンヌレ、シャルロット・ペリアン《バスキュラントチェア(No.LC1)》カッシーナ[トーネット社] 1975年 [1928年]、武蔵野美術大学 美術館・図書館、ポーラ美術館 Photo: Alma Reyes
しかし、アール・デコの装飾性を批判する者もいた。建築家ル・コルビュジエは、アール・デコ博に対抗し、当時会場となったグラン・パレの裏手の場所を勝手に占拠し、あえて装飾のないパビリオンを建設した。本展では、スチールとレザーを組み合わせ、機能性と快適性を備えた《バスキュラントチェア(No.LC1)》(1975年 [1928年])をはじめ、コルビュジエが手がけた名作チェアを展示している。

ジョルジョ・デ・キリコ《ヘクトールとアンドロマケー》1930年頃、ポーラ美術館 © SIAE, Roma & JASPAR, Tokyo, 2023 B0685
機械の発達は、近代化に抵抗する動きも引き起こした。1910年代には、欧米の各都市で芸術のシステムに異を唱える芸術運動「ダダ」が起こり、1924年にはアンドレ・ブルトンが「超現実」を芸術によって探究するシュルレアリスムを創始し、「シュルレアリスム宣言」を発表。シュルレアリスムは機械時代を支える合理主義を批判的に捉え、目的を持つ機械とも、造形的な美しさを探究する彫刻とも異なる、「オブジェ」という新たな概念の立体作品を生み出した。ジョルジョ・デ・キリコの《ヘクトールとアンドロマケー》(1930年頃)は、ホメロスの『トロイア戦争』という古典的なテーマを想起させ、シュールレアリスティックなマネキンに変身した2人の恋人が別れを惜しんでいるようにも見える。

杉浦非水《東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通》1927年(昭和2年)、愛媛県美術館[展示期間:2023年12月16日〜2024年3月1日]
日本では1923年(大正12年)に発生した関東大震災からの復興により、急速に近代化が推し進められた。多くの芸術家たちがフランスやドイツに渡り、前衛の思想を持ち帰った。杉浦非水もそのひとりで、日本の近代商業デザインにアール・デコを導入した先駆者となった。ポスター《東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通》(1927年/昭和2年)は、東京の地下鉄開通を告げるもので、遠近法を用いた明快で力強いデザインによってモダン都市・東京を表現している。
続きを読む ...