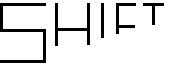生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界
HAPPENINGText: Alma Reyes
日本美術の歴史の中で、女性の肖像画は常に好んで描かれてきた。江戸時代の木版画や伝統的な絵画には、花魁、女武者、歌舞伎の女形、あるいは妻や母親といった女性の姿が描かれてきた。大正時代を代表する画家といえば、竹久夢二(1884-1934年)の名が浮かぶ。「大正ロマン」を象徴する画家であり、詩人でもあった夢二が描く「夢二式」と称される女性の心情や内面を描いた美人画は、儚く頽廃的な雰囲気に包まれている。
東京都庭園美術館で竹久夢二の展覧会「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」が、8月25日まで開催されている。本展は、生誕140年を記念して、夢二の画業にまつわる絵画や素描、スケッチ帖など、初公開資料を含む約180点の作品を夢二郷土美術館コレクションを中心に紹介するもの。

竹久夢二《アマリリス》1919(大正8)年頃、カンヴァスに油彩、夢二郷土美術館蔵
夢二の油彩画は現存するだけでも約30点と少ない。本展の最大の見どころは、長らく所在不明で近年の調査により発見された大正中期の名画《アマリリス》(1919年)だろう。着物姿の女性はプロのモデルで、後に夢二の恋人になったとされているが、真っ赤なアマリリスの花の鉢のそばに座り、感傷的な目でじっと見つめている。彼女の唇や肌着にも同じ赤のアクセントが差されている。この絵は“夢二のモナリザ”と呼ばれており、発見後、東京で初めて公開・展示される貴重な機会だ。

竹久夢二《晩春(雑誌『グラフィック』第1巻第1号 口絵原画)》1926(大正15)年、紙に鉛筆・ペン・水彩、夢二郷土美術館蔵
この展覧会では、日本の「ベル・エポック」とされる大正ロマンの重要な流れを明らかにする。「大正」と「ロマン」という2つの言葉は、夢二の作風が和と洋の美意識に包まれたロマンチックなムードを醸し出したことに呼応して組み合わされたと言われている。《晩春》(1926年)、《立田姫》(1931年)、《湖畔舞妓図》(昭和初期)、《西海岸の裸婦》(1931-1932年)など、夢二独特のタッチで描かれた魅力的な女性の表現は、同時代の画家たちにインスピレーションを与えた。大きく潤んだ瞳、儚げな体の曲線は夢二の典型的なアプローチである。19世紀末から20世紀初頭にかけて、アーツ・アンド・クラフツ運動、アール・ヌーヴォー、アール・デコへと時代の移ろいとともにその理念は変化させつつも、夢二は一貫して「生活の中の美」を追求し続けた。

竹久夢二《西海岸の裸婦》1931-32(昭和6-7)年、カンヴァスに油彩、夢二郷土美術館蔵
夢二は生涯を通じて芸術で人々の暮らしを彩ることに関心を向けた。本展の会場となる東京都庭園美術館の本館は、かつて朝香宮家の自邸であった場所で、実際の生活空間に施された多彩な装飾が見所となっており、本展は、暮らしの中の美を体現する邸宅空間の中で、夢二の作品世界を鑑賞できる理想的な会場となっている。
晩年の1931(昭和6)年から約2年間、夢二は、欧米各地を巡る旅に出かける。1930年代前半は、モダンな芸術と都市文化が急速に発展する一方で、ナチズムが勃興する不穏な時代でもあった。夢二は欧米滞在中の出来事を多数のスケッチとして残しており、西洋の芸術的要素を取り入れながら、現代社会のリアルなイメージを現出させた。そのスケッチは、海外での夢二の足跡を伝える歴史的な資料ともなっている。
続きを読む ...