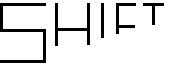「キャンプ・ベルリン」展
HAPPENINGText: Yoshito Maeoka

ダヴィッド・ポルツィン《フェルテン |》2008
観客が自ら“移動する”体験に焦点を絞ったのは、ダヴィッド・ポルツィンの作品だった。彼は会場内に小さいながらも自らの聖なる神殿を構築した。その神殿の中を一目見ようとする鑑賞者は、ゲートにてコントロールであるアーティスト本人に身分証を提示し中に入る必要があった。空港等の越境コントロールと同じ構造を再現することにより、鑑賞者は架空の領域に足を踏み入れなければならなかった。

マリー・ルイーゼ・ビルクホルツ《私もそれについては何の関係も持ちたくない。》2008
マリー・ルイーゼ・ビルクホルツの作品も観客の移動を作品の要素に撮り込んでいる。壁にライトを設置し、その手前に植木を設置した。この構造は典型的なドイツの一戸建てに於ける公共空間としての前庭とプライベートな空間に一致する。

エリック・アルブラス+イレーネ・ペツーク《ヴァンデルング(ハイキング)》2008
また、展覧会のテーマ「マイグレーション」をユーモラスに解釈したのは、エリック・アルブラスとイレーネ・ペツーク、古堅太郎だった。エリック・アルブラスとイレーネ・ペツークは、会期中徐々に “移動する” 壁を設置した。

古堅太郎《Untitled》2008
壁に一枚の白い板が立てかけられていた。この白い板は壁と同じ素材の様だが、周辺が薄く汚れていた。古堅太郎は展覧会の設置に際して使用した壁材に炭をかけて、手形や指紋を浮き上がらせた。設置の際、人々の仕事の跡が残ることにより、会場を設営したアーティスト達、すなわち移動する今回の主役達が彼の作品の中の主人公となった。
続きを読む ...
【ボランティア募集】翻訳・編集ライターを募集中です。詳細はメールでお問い合わせください。